丹羽 憲治・孝太郎
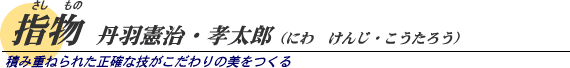

ドアを開けると、丹羽さん父子が板の間に座って黙々と作業を続けていました。
「私で3代目になります」
息子の孝太郎さんは、幼い頃から見てきた父親の作業を見よう見まねで覚え、「なるべくしてなった職業」だといいます。が、父親の二代目、憲治さんは「別に強制した事もないし、やれと言った事もないんだけどね」と言いながらも後継者不足の匠の世界で、親から受け継いだ技を次の世代に橋渡しできる事を素直に喜んでいる様子。
憲治さんがこの世界に入ったのは兵隊から戻ってきた23才のとき。孝太郎さん同様、父親の仕事をずっと見て育ってきた事で、当たり前のように父親の跡を継ぎました。
「一番むずかしいのは、正確にはめ込む事ですね」板と板を釘を使わずに組み指し合わせる指物師は、少しの隙間もなく、寸分違わず正確に箱を作る技術が要求されます。板に少しでも反りがあると作れないことも含めて、まさに長年の技術の積み重ねと職人としての勘所によるもの。
作家ものの湯のみや茶碗入れ、時にはお猪口入れなどのようなわずか一辺4~5センチの箱から、最大では「長さが六尺だったかなあ」というほどの大きな屏風入れまで、注文に応じての制作。「本来は、屏風を作る職人さんと組んでる指物師がいるんですが、箱を新しくするという時などには注文が来ます」
朝8時半には親子で作業場に座り、昼食に一時間取る以外は夕方5時半まで座りっぱなしで作業を続ける丹羽さん。「素材は桐です。でも、桐にはランクがあって、値段も10倍くらい違うんです」 依頼者の要望に応じた桐を使用。茶器や茶道具を入れる箱は上等の桐を希望する場合が多いそうです。
まずは寸法を計り、桐の板を切り出し、木工ボンドで接着して組み立てます。
「昔はご飯粒でくっつけてたものです」
作業場の引き出しには、自作した大小何十というカンナなどが収まり、匠の歴史を物語っていました。
東麻布一丁目

