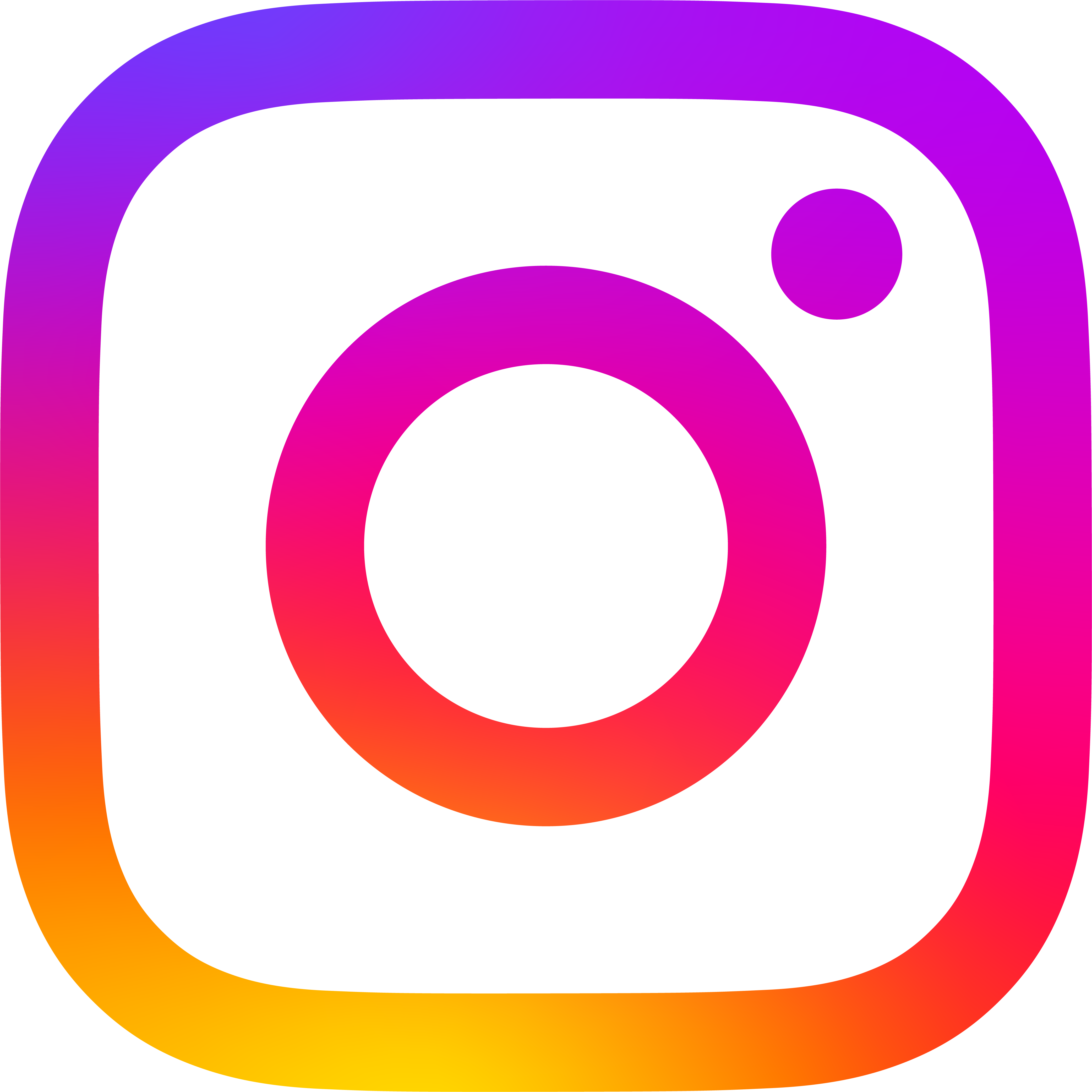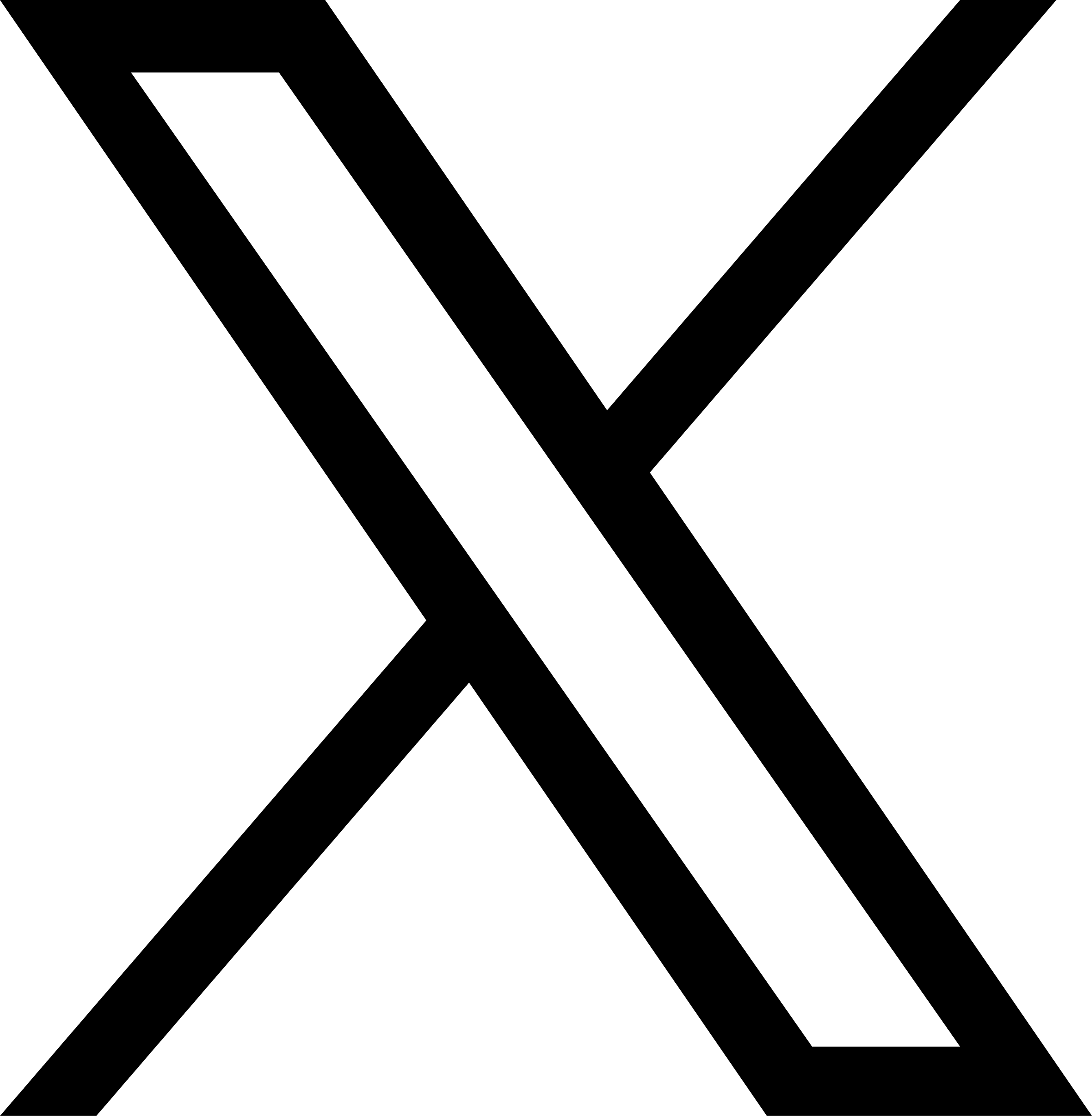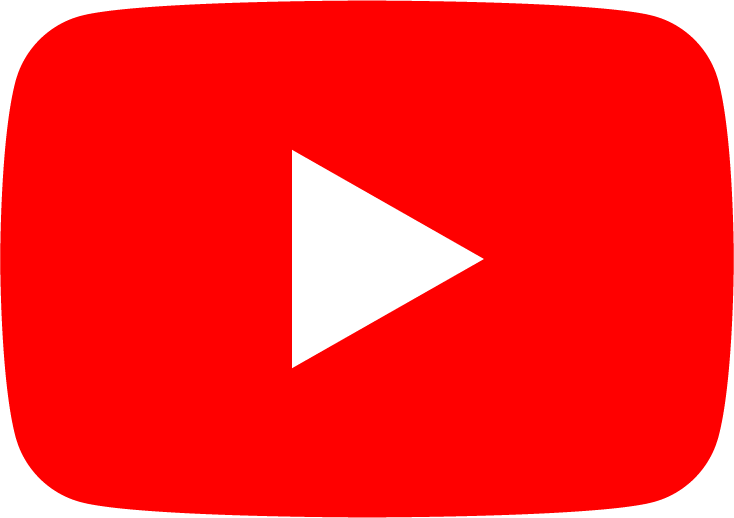株式会社サステナブルエデュケーション
株式会社サステナブルエデュケーション
子どもの主体性を育む
理想のプリスクールを開園

株式会社サステナブルエデュケーション
代表取締役中川 早智子さん
代表取締役
中川 早智子さん/Sachiko Nakagawa
■経歴
大阪府で私立幼稚園勤務を経て渡豪。オーストラリアでのチャイルドケアワーカー、日本語教師の経験を通じ、子どものための教育について深く考えるようになる。ドイツではアドラー心理学を取り入れたプリスクールや、NGO ドイツ国際平和村での乳幼児保育に携わる。 帰国後は、外資系IT 企業を中心とした人材採用業務に携わるなかで、思考力を持ちグローバル化にも対応できる人材育成に向けての幼児教育の重要性をより強く感じるように。日本に暮らす子どもたちへの多様な教育の機会づくりに貢献するため、Pikkas International Preschool の開園を決意。
海外での幼児教育の経験を生かし、
理想のプリスクールを開園
―今年、港区芝浦にプリスクール「Pikkas」を正式開園します。どんな園ですか。
「Pikkas」は遊び主体の保育、オールイングリッシュが特徴のプリスクールです。私自身が海外の幼児教育に携わってきた経験をもとに、モンテッソーリやアドラー心理学などの様々な教育哲学を取り入れ、子どもにも保護者にも教職員にも心地よい「三方よし」の保育を提供していきます。
自然素材を取り入れた施設、できるだけ添加物を使わない給食、オーガニックコットンでできたユニフォームなど、細かいところにもこだわって子どもたちの成長を見守ります。
―子どもたちは「Pikkas」でどんな1日を過ごすのでしょうか。
朝8時半から開園し、1日のはじめには身体を使うエクササイズをしたり、先生との対話の時間があります。そこで一定の年齢以上の子どもたちには、その日何をして遊ぶかを決めてもらいます。
これが「Pikkas」が大事にしている選択保育です。自分の遊びをしっかりと決めて遊び、遊び終えたら片付けて次の遊びに行くという流れを身につけてほしいと思っています。いずれ、外の行き先もみんなで相談して決めていきたいです。
毎日自分で遊びを決めるだけではなくアートやサイエンスなどの様々なアクティビティも用意しています。ただ、ほかのことをしたい子もいますから、必ず全員で一斉に座って活動をするわけではありません。発表会や作品づくりなどといった目に見える成長は、ほかの園よりも感じづらいかもしれませんが、その分日々の小さな成長を感じて頂けるよう毎日の連絡やドキュメンテーションを行います。子どもたち自身が「明日、何をしようかな」と考える力は身についていくと思います。
先生の数も基準以上を提供していますが、多ければ良いとは考えていません。子どもの自主性を育むためにも、あまり先生がこまめに指示を出したり教えたりはせず見守り、子どもが困ったときに手を差し伸べるというスタイルにしています。
―2024年12月には「Pikkas」で、ドイツ発祥のボールやアスレチックでの遊び運動「バルシューレ」を子どもたちが体験するイベントを開催しました。反応はいかがでしたか。
子どもたちは本当に楽しんでくれていたと思います。思い思いに遊んでいましたね。園に入った瞬間から遊具をめがけて走ってきて、何の指示がなくても勝手に遊んでいました。「どうすればいいのかな」と途方にくれる子どもは誰一人いませんでしたよね。 大人の場合は、「ここでどう振る舞えばいいか」と考えたり、「これを使っていいですか」「触っていいですか」と聞いたりしますが、自分から主体的に遊ぶことで挑戦する心も培われていきます。
子どもによって成長段階の違いや、得意、不得意があるので、地面からの高さがあまりない遊具で遊んでいても、その子にとっては挑戦です。それぞれの子にとって少しでも難しいものに挑戦する時間が大切だと思っています。
子ども自身が遊びを選ぶことで、
自分で考え、意見を言える子に
―「Pikkas」を開園した理由を教えてください。
もともと新卒では幼稚園の先生をしていました。やりがいのある仕事ではあったのですが、1人で35人の子どもを見たり、長時間労働をしたりという状況はなかなか大変で3年間の勤務を終えて退職し、オーストラリアに渡ってチャイルドケアワーカーや日本語教師として働きました。
もともと英語が得意だったわけではないのですが、海外で過ごす中で世界も広がり、「英語が話せるとこんなこともできるんだ」と思うようになりました。帰国後は、海外出張もある仕事に就きたいと思い、商社で2年半ほど働きました。
そしてまた海外に行きたくなり、ドイツのプリスクールや、病気やケガをした世界各地の子どもを治療する「NGOドイツ国際平和村」で、保育士やインターンシップの仕事を経験しました。そこで出会った各国の子どもたちは「医者になりたい」「学校の先生になりたい」「もっと勉強したい」と、主張や意思がはっきりしていて、日本で教育を受けている子どもたちと比べると未来を語る目の輝きが全然違っていたのが印象的でした。日本の子どもたちは大人に何かを指示されたり、やらされたりすることが多く、好きなことに没頭する時間が限られているからではないかと思いました。
その後帰国し、いったん人材採用の業界に入りましたが、面接で自分の意見をきちんと言えるか、自分なりの仕事の経験をきちんと語れるか、ということが大事だと痛感しました。また、日本語も話せる英語ネイティブの海外の方が企業の管理職のポストに就いていく様子を目の当たりにし、日本人ももっと英語を話せる人が増えた方がいいとも思いました。
こうした海外での経験や、人材採用業界での気づきから、自分の頭で考えて意見を言える子、英語を話せる子を育てるプリスクールをつくりたいと考え、具体的なコンセプトが固まっていきました。
―2、3歳まで日本語で育ってきた子は、どのようにして「Pikkas」で英語を話すようになるのでしょうか。
私もこれからがとても楽しみです。ドイツ国際平和村にはアンゴラやアフガニスタンなど様々な国の子がいましたが、3ヶ月くらい経つとみんなドイツ語で流暢に会話するようになっていました。当園へ通う園児さんもオールイングリッシュの環境のなかで登園2日目から”Thank you!” “Wash, wash”, “Wait wait”と早速たくさんアウトプットしています。
2歳くらいの子だと言語の習得力や環境になじむ力は強いので、周りが英語で話していたら英語を自然に話すようになっていきます。4歳くらいになると、自分で自分の気持ちを伝えることもできるようになります。ですから、「『このおもちゃで遊びたい』って英語で何て言うの?」と先生に日本語で積極的に聞いてもらうのも良いですね。話そうという気持ちがあるとどんどん伸びていくので、英語で話す場だということを理解した状態で入って、どんどん話してほしいですね。
―ドイツやオーストラリアの幼児教育は、日本とどのように違いましたか。
日本の幼児教育では、体操や劇や楽器、学習目標や試験など、たくさんの達成目標がある園も多くあります。もちろんそれも楽しいですし、クラスごとのばらつきがなくなるというメリットもありますが、ずっとやることに追われてしまい、自分の頭で考えて何かをする時間は少なくなってしまいます。 ドイツやオーストラリアでは、自分で選んで遊びを決めるという機会が多かったですね。自分で考え選択すると、ときには困ったり失敗したりすることもありますが、そうした経験を経て子どもたちは困難に立ち向かう力を身につけていきます。
理想のプリスクール開園を目指し
一般企業でビジネススキルを習得
―帰国後、プリスクールを立ち上げるまでには、どんなことに取り組んでいましたか。
ドイツから帰国した後、一度は東京のプリスクールに転職しようと思いましたが、自分が理想とする園にはなかなか出会えませんでした。そこで私自身がプリスクールを開園しようと思い、足りないビジネススキルを身につけるためにも企業で経験を積もうと考えました。企業で働いている間も時間を見つけては幼児教育のセミナーに参加し、世界各地の幼児教育について学んでいました。
―一般企業でのビジネス経験は、起業においてどのように役立ちましたか。
企業では本当にいろんなことを学びました。人事業界を中心に経験を積んできたのですが、例えば人材会社では「面接を週3回行うというノルマを達成するなら、1日10人に声をかけないといけない」というシビアな数字を意識していました。
それはプリスクールの経営にも生きていて「15人集客するなら、何人説明会に来てもらおう。そのためには何をしないといけないか」ということを常に考えてきました。
―企業でのビジネス経験を積んでいても、起業して初めてぶつかった壁もあったのではないでしょうか。
起業するにあたっては知らないことが多く、「TOKYO創業ステーション」で相談を続けました。それから港区立産業振興センターにも登記して専門家に補助金の情報を教えていただき、港区の創業助成金や小規模事業者持続化補助金などを受けました。初めての起業でしたから、困ったときの相談相手がいるというのは、とても心強かったですね。
認可外保育所は、認可保育所であれば受けられる自治体からの助成金もないので、本当に運営が難しいです。運営費や設備費も全て自己資金と融資でまかなっていますし、維持費もかかります。自治体の制度も頻繁に変わるので、対応も大変です。プリスクールは保育料が高く「お金持ちのためのビジネス」と思われがちですが、実際は大変なことだらけです。それでもやりたい、という気持ちがないと難しいだろうなぁと自分でも思います。
―スタッフはどのように集めましたか。
人事業界を中心に経験を積んできたため、採用は得意領域なので、有料の求人媒体は使わず、直接ダイレクトメッセージを送るなどして自分で採用を進めていきました。結果として100人以上の方から応募をいただき、プリスクールでの勤務経験がある関東在住の方50人以上とオンラインやリアルで面談していきました。 幼稚園の先生の働き方に課題を感じている方や、「Play based learning」(遊びを通して学ぶこと)の考え方を大事にしている先生には、興味を持っていただきやすかったです。私にとっても、いま幼稚園で働いている先生のリアルな声を聞くことは勉強になりました。
起業のアイデアを人に話すうちに、
つながりが増えていく
―港区芝浦でプリスクールを開園した理由を教えてください。
港区は日本一プリスクールへの関心が高い地域だと思います。外国人の居住率も高いですし、インターナショナルスクールにも寛容です。 そんな港区の中で、芝浦は子どもが多いのにプリスクールが少ないエリアでした。日本人のご家庭に対して、オールイングリッシュの環境を手軽に届けたいという私の思いにマッチする地域だと思いました。 それから、スクールバスで通園してもらうよりも、徒歩通園の方が保護者と先生が毎日、顔を合わせることができますよね。徒歩圏内の地域の子どもで園の定員が埋まるという高い目標を目指し、総合的に判断して芝浦を選びました。
―開園に向けて、手ごたえはいかがでしょうか。
入園を決めてくださった1人目の方には本当に感謝しています。2人、3人と入園者が決まってくると風向きが変わったように感じましたが、最初に施設も完成していない状態で決めてくださったのは本当にとてもありがたかったです。
入園を決めてくださる保護者にほぼ共通しているのは、私が掲げている理念に共感できる原体験があるということですね。「全員一斉の活動が多い園に通っていた上の子が、園嫌いになってしまった」「身の回りで教育虐待のような事例を見ていて、疑問を感じていた」「英語が話せたら、もっとできることが増えていたのに、と思っていた」「職場で主体性の大切さを痛感している」といった経験をお話しくださる方が多いのではと感じています。
―今後の展望や目標を教えてください。
まずは毎月、黒字をしっかり作っていくことが第一目標なので、園児を集めることに注力していきます。徐々に園の基盤ができてきたら、保護者のニーズも聞いてサタデースクールやアフタースクール、2つ目、3つ目の園の事業計画も着手していきたいです。 定期的なイベントや土曜日の開園のためにもスタッフは増やしていきたいですね。まだアイデア段階ですが、園内向けにはパジャマを着て映画を見るムービーナイトや、東京から離れた自然の中での活動など面白いイベントも企画していきたいです。 それから、アフタースクールのニーズについても、子ども達が英語環境で過ごせるアフタースクールも開けたらいいですよね。 やってみたいことはいろいろあるのですが、自分の子どもとの時間も大事なので、1日8時間でどこまでできるか、挑戦中ですね。いずれ70歳になった時にも園長先生として園児たちに囲まれた毎日を過ごして、卒園した子が「あそこの園の出身なんだ」と言ってくれるようになればうれしいですね。
―起業を考えている人に向けたメッセージをお願いします。
アイデアややりたいことがあったら、とにかく人に話すといいと思います。最初はアイデアを人に話すことを恥ずかしく感じるかもしれませんが、私もプリスクールをつくりたいと周囲に話していたら、人や施設を紹介してもらえて、つながりが増えていきました。少しでもやりたいことがあったら、「バカバカしい」とか「自分は何も持っていないから」などと思わず、まずは人に話してみることが大事だと思います。
資金面については、もちろん1円でも多く貯金していた方がいいとは思います。ただ、事業を立ち上げるまでお金はかからないので、「お金がかかるから立ち上げられない」と尻込みする必要はないと思います。 今は自治体の起業支援も充実しているので、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
記事投稿日:2025年2月15日