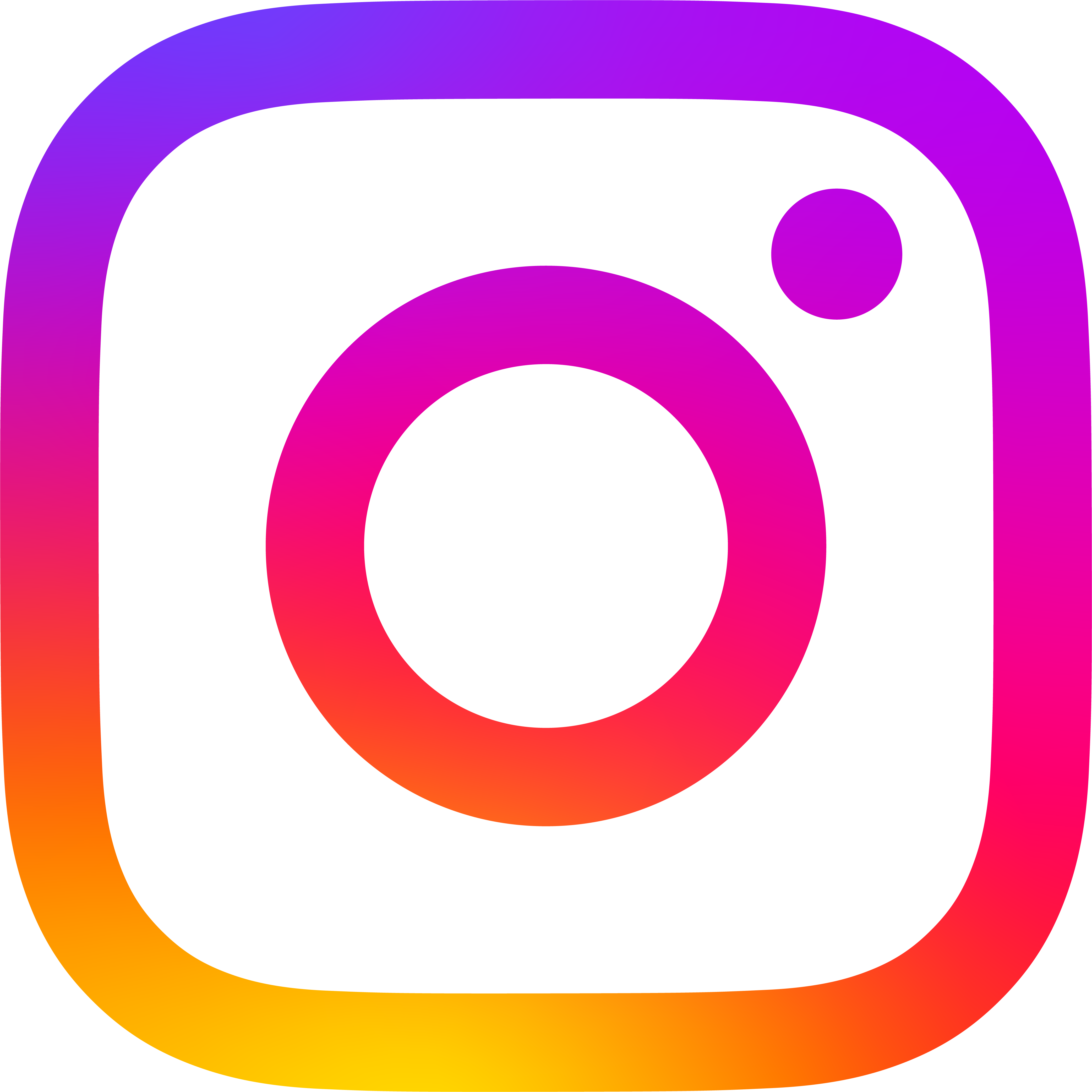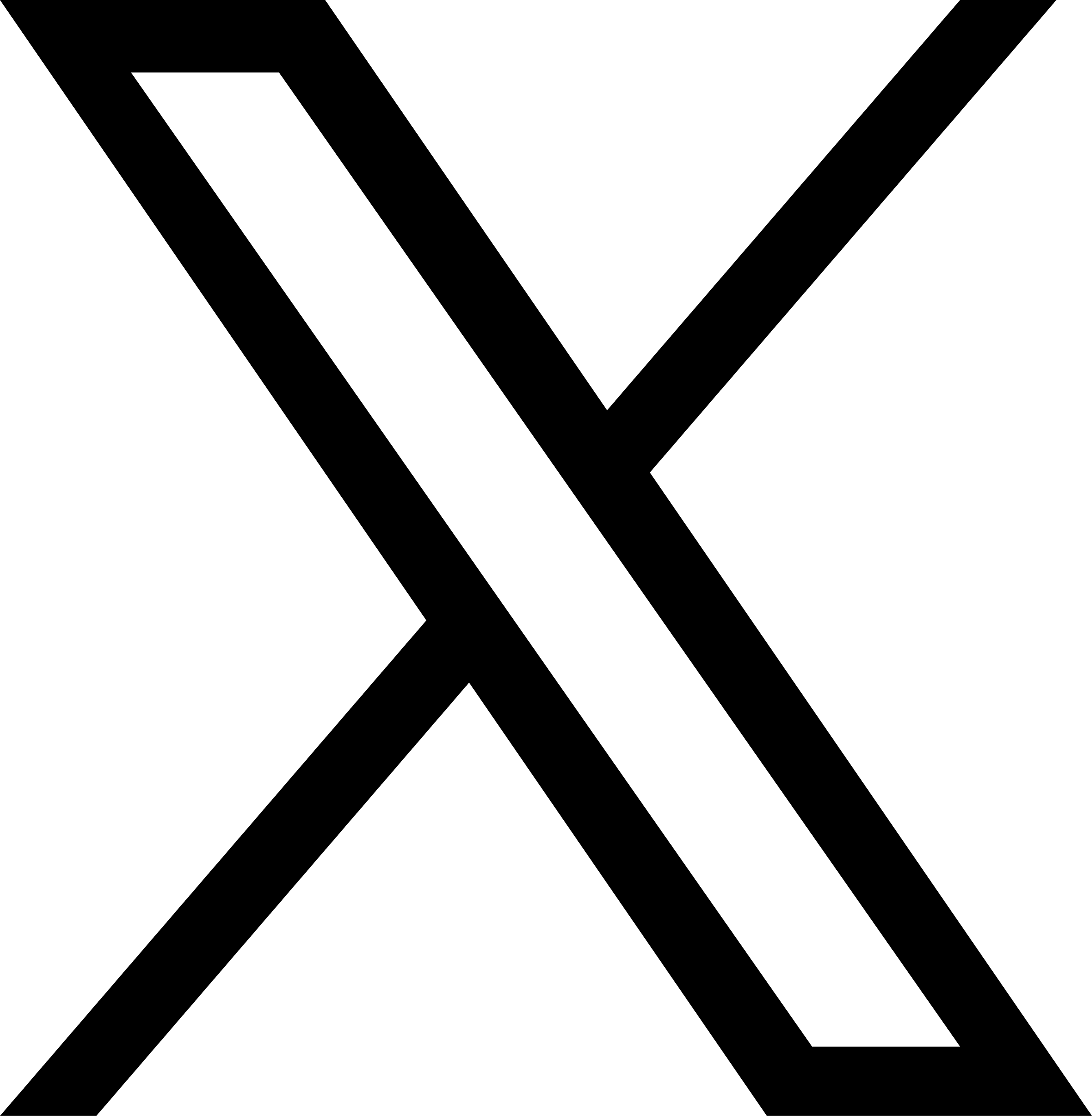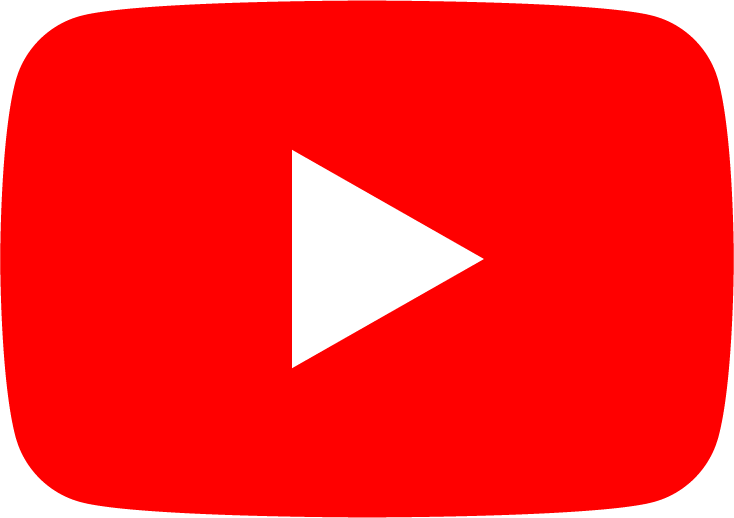株式会社モリアゲ
株式会社モリアゲ
農林水産省から起業家へ
日本の森をモリアゲる

株式会社モリアゲ
代表長野 麻子さん
代表
長野 麻子さん/Asako Nagano
■経歴
東京大学文学部フランス文学科卒、1994年に農林水産省に入省。 2018年から3年間林野庁木材利用課長として「ウッド・チェンジ」を各地で叫び続ける。豊かな森を次代につなぐことを勝手に天命と感じ、2022年6月に早期退職。同年8月に日本の森を盛り上げる株式会社モリアゲを設立。
森のビジネスで利益を出し、
森に再投資して「モリアゲ」たい
―森林の有効活用に関するコンサルティングなどを行う「モリアゲ」を立ち上げた思いをお聞かせください。
森は、美味しい空気や水を提供し、様々な生き物を育む、私たちの生活に欠かせない自然資本です。私は林野庁で仕事をしていた経験もあり、「日本の地方の多くには森があるから、森が元気になれば日本が元気になる」という思いで、2022年8月、「モリアゲ」という会社を立ち上げました。会社名は、ある日パッと思いつきました。その名の通り、「日本の森をモリアゲる」という意味を込めています。
森からの収入はこれまで、木を切って売る林業が一般的でした。ですが今は、それだけではありません。地球温暖化を防止する、生物を育むといった環境価値をお金にできる時代が来ました。
木を切らなくても、森林浴や企業研修など森林空間を生かしてウェルビーイングを目指すビジネスで利益を生み出し、森に再投資することで森を維持し活性化させていきたいです。そんなことを考え、森を有効活用したい企業や自治体などにアドバイスをしたり、関係する方々同士をおつなぎしたりしています。
森を生かすビジネスを若い人たちがどんどん始めてくれれば、森も地方も盛り上がりますよね。そんな思いで、森と街、人との橋渡しをしています。
―もともとは農林水産省で働いていましたよね。
はい。林野庁の木材利用課長として、森を循環活用するために鉄やコンクリートを木材に代える「ウッド・チェンジ」というプロジェクトに携わったことが、森への関心を高めるきっかけとなりました。森がなければ、きれいな水もありません。海だって、森からミネラル分が流れているんです。だから、農業も漁業も全て豊かな森があることが大事なんです。そのことに改めて気づいて森への思いが高まり、ずっと林野庁で仕事をしたいと思っていたのですが、その後は異動し、森と離れた仕事をすることになりました。もちろんその仕事も大切なのですが、森に貢献したいとの気持ちが抑えられず、残りの人生の時間は森のために使いたい、自分が森のために何かできる環境を作ろうと思い、起業しました。
―NPO法人の立ち上げなど、他にも選択肢はあったかと思いますが、起業を選んだのはなぜですか。
株式会社として地球に優しいことや環境に役立つことをして儲けて、さらにその利益を森に再投資したいと思ったからです。NPO法人やボランティア団体では、なかなか利益を大きくは生み出せません。株式会社の方が、森に対して持続的に利益を還元していけると考えました。
やってみると、株式会社を作るのは意外とそんなに難しくないですよ。私は退職金の一部をつぎ込みましたが、資本金が1円でも設立できます。それまでビジネスをした経験はありませんでしたが、定款作成や登記の手続きも行政書士の方がやってくれたし、森に関わるビジネスをしたい企業や、地域の森をなんとかしたい自治体等にアドバイスやセミナーをすることでお金をいただけるようになりました。
―官僚を辞めて起業すると、働き方が大きく変わったのではないでしょうか。
毎日、全国各地のいろんなところに行くのは新鮮ですよね。そして何より自由に、楽しく仕事をしています。官僚時代も楽しかったですが、起業してみたらもっと自由で楽しいですね。 もちろん役所も規模が大きく、責任のある仕事をできますが、今は自分で全ての責任を持って、上から与えられた仕事ではなく、自分で選んだ仕事をできる喜びがありますね。
ただ、役所での経験やネットワークがあるからこそいただいている仕事もたくさんあるので、役所にいた経験が決して無駄だったというわけではありません。森の分野は、官と民が一緒にやらないと、うまくいかないことが多いんですよね。だからこそ、官から民の立場になった私がいろいろな人や企業、団体をつなぐ役割をしていきたいと思っています。
―仕事に対する姿勢はどう変わりましたか。
役所で働いていたときには、仕事は課題から始まっていました。「この課題を何とかしなくちゃ」という思いで政策づくりをしていましたが、起業してからは「こんな可能性がありそう」「こうなったらいいよね」と思うことに取り組んでいます。
山に関わっている方々からは「これまでずっと儲からなかった」「年をとって先がない。山じまいをしたい」という声もよく聞きます。山を持っていてもお金にならないから諦める、という方が多いのですが、私から見ると、森林は可能性の塊です。森林を手入れする人たちにきちんとお金が回る仕組みを作って、森林の可能性を信じる人たちを応援したいですね。
「一社一山運動」で
森が維持される世の中を目指す
―最近とくに力を入れている事業はありますか。
企業に自分事として森林に関わってもらう「一社一山運動」に力を入れています。森には土砂災害を防止する、水を蓄える、空気をきれいにするといったさまざまな役割がありますが、そこには実は70兆円ぐらいの価値があると言われています。森の恩恵を受けていない人や企業はいないので、そういう恩恵を末永く受けられるようにするため森にお金を払って森の整備を進めることで、森を次代につないでいけたらいいなと思っています。
特に資金力のあるのは企業なので「一社一山運動」を提唱し始めました。まず隗より始めよということで、長野県木島平村の国有林でブナ林の再生活動をしており、最近はソフトバンクさんや姉妹都市である調布市の市民の方々もこの運動に参加してくれています。
―クライアントは企業が多いのですか。
自治体や企業が主なクライアントです。企業は森や木に関係のない事業をしているところがほとんどですが、最近はサステナビリティ経営が注目されていることもあり、「森や自然を活用して、何かできないか」という相談を受けることも増えてきました。そこで、木材の伐採現場を見てもらったり、森の保全活動に参加してもらったりと、森に行くきっかけを生み出すようにしています。
そのほか、自治体や団体で森をモリアゲるためのヒントとなる講演をしたり、自治体や山主からの相談を受けたりすることもあります。
―起業したときに、収益面や資金面の心配はしませんでしたか。
ノープランでしたね!「案ずるより産むが安し」「なんとかなる」というスタンスでした。起業してみると、役所時代のネットワークのおかげで、自治体や森林組合、企業からお声がけをいただくことが増え、ありがたく思っています。
「こういうことをやりたい」と言っていたら、「ここにこういう人がいるよ」とか「こういう研究者を紹介するよ」と声をかけていただくことも多いです。だから、やりたいことが十分に言語化できていなくても、周りにどんどん言うことが大事だと思っています。
―起業後、壁にぶつかったことはありますか。
大企業の担当者が森に関する取り組みに関心を持ってくれても、社内の決裁が下りず立ち消えになったというケースにはときどき直面します。大企業は資金も人材も潤沢なので新規事業がスムーズに進むのかと思っていましたが、意外とそうでもないんですよね。打ち合わせにばかり時間をとられ、結局企画が通らずにお金をいただけない、ということが最初のころはありましたね。
ただ、こうした経験も自分でビジネスをやってみないと分からない、貴重な学びですよね。それからは、毎月コンサルティングをして、定額をいただくビジネスがいい、という感覚もつかめてきました。今は起業して2年ちょっと経ちましたが、2年間とも黒字で経営できています。森で儲けたお金は森に還すと決めているので、利益は森をあきらめない自治体に企業版ふるさと納税をしています。
※長野県木島平村での一社一山の取組
森や地域をリスペクトし、
ともに価値を生み出していく
―森や自然に関する、企業の最近の取り組みをどう見ていますか。
森を綺麗に豊かにすることで、ネイチャーポジティブ(自然再興)にも貢献できると考える方々が増え、森へのインパクトの定量化手法も進んできて、森林に関する取り組みのためにお金を出す仕組みができつつあると思います。
「モリアゲ」が利益を上げていること自体、森に注目が集まっているということでしょうし、いろんな企業から相談を受けるのはありがたいことです。徐々に追い風が吹いているので、これを一過性のブームにせず、企業の皆さんには森と長く付き合ってもらいたいと思っています。
―企業はどのように森を活用していけるでしょうか。
従業員の皆さんにもときどき森でリフレッシュしてもらって、元気に働いてほしいと思います。社員のウェルビーイングや健康経営の考え方にも、どんどん森をとり入れてほしいですね。
森で働いている人たちはみんな元気ですよ。元気な人しか木こりにならないということもありますが「森の力かな」なんて思っています。実際、森林浴による免疫力の向上といったエビデンスも明らかになってるんですよ。緊張する場面の多い起業家の皆さんにも森に行ってほしいですね。自然の中でリラックスしてほしいです。さらに、日本の森をめぐる状況は、無関心、木材自給率の低さ、管理する人手の不足など課題だらけなので、ビジネスチャンスはたくさんあると思います。皆の知恵や技術を集めて、森の課題を解決できたらいいですよね。林業をしている人たちだけでは、解決できないことがたくさんあるので、異業種の人たちが入ってきて目線が変われば、できることも増えると思います。
―森や自然に関することで起業したいという方に向けてのメッセージはありますか。
あくまで森や地域の人たちへのリスペクトを忘れてはいけないと思います。その地域がたどってきた歴史や文化をリスペクトしたうえで、コラボしたり、新しい価値を生み出したりしていくという姿勢が大事です。「俺が外から行って、自分だけで何とかしてやろう」という態度では受け入れられません。でも実際に森がある地域の方々に会ったら、魅力的な人が多くて、みんな好きになると思いますよ。
それから、森に関するビジネスに限らず、何歳になっても起業は楽しいということを伝えたいですね。私は50歳になってから起業して全国を飛び回っているので、体力的にきつく「もっと早く起業していれば…」と思うこともあります。ただ、農林水産省で30年近く勤めた経験があったからこそいただけている仕事、できる仕事もたくさんあるので、何歳で起業しても遅くないと思います。人生は短いので、ぜひ挑戦してみてください。
※岡山県西粟倉村でのチェンソー特別講習
森に関わる皆がつながり合い、
「モリアゲ」がいらなくなるのが夢
―「モリアゲ」の今後の展望はいかがですか。
今はいろいろな自治体や、森の保全活動をしている団体、企業などをつなげて森を「モリアゲ」る活動をしていますが、いずれは皆がつながり合い、それぞれが森を「モリアゲ」てくれれば、「モリアゲ」という会社はなくなってもいいと思っています。今はあまりにつながっておらず森の有効活用ができていないので、私がつなぎ役になっていますが、「モリアゲ」がなくなるのが夢、と言ってもいいかもしれません。
―「モリアゲ」がなくなるまでに、まだまだ長野様の役割はたくさんありそうですね。
日本で森を想う人の割合を、国土に占める森林の割合と同じ7割にしたいと思っているので、森とつながりを感じられる人を増やしていきたいですね。最近は、猫の好物として知られるマタタビを集めるプロジェクトを通じて、猫好きの人に森を訪れてもらおうと考えています。それから、胃腸の弱い人の生薬として使われてきたキハダの木を探す活動も応援するつもりです。
さらに大きなことを言うと、森に行く人たちを増やしたいので、もっと気軽に森林浴に行けるような森を増やしたいです。ヨーロッパの方々は日常的に森に行くんですよ。日本だとせっかく国土の7割を森林が占めていますが、簡単に行ける森は少ないですよね。登山までしなくても、単に森でぼーっとするとか、コーヒーを飲むとか、ちょっとした散歩をするとか、そんな風に気軽に森に行けるように、森に対するイメージを身近なものにしたり、歩きやすい森をつくったりしたいですね。
―森に関するビジネスチャンスはまだまだありそうですね。
もともと「森林浴」という言葉は、1982年に当時の林野庁長官が提唱した言葉です。それが今や、海外に「SHINRIN-YOKU」という言葉で広まり、日本より盛んになっています。せっかくなら森林浴発祥の地の日本で、日本ならではの森林浴をしたいという外国の方もいるのではないでしょうか。たとえばフランスの森林は平坦ですが、日本の森には傾斜があり、フランスとは違った景色を楽しめます。今は英語の案内がある森は少ないので、そうしたところにもビジネスチャンスがありそうだとも思っています。外国人向けの森林浴ツアーも面白そうですよね。
それから、いずれ「モリアゲ」で山を買いたいという野望もあります。今年チェンソー講習を受けたので、今後ユンボの免許をとって、理想の森づくりをしてみたいんです。
まだまだノープランですが、夢は広がっていますよ。
記事投稿日:2025年2月13日